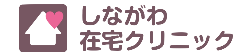便秘薬は市販でも各メーカーから様々な種類が発売されています。その種類の多さから、どれを選べば良いのかわからなくて困ったという方もいらっしゃるのではないでしょうか。便秘薬の中には長期服用することで重い副作用を生じるものや、耐性ができて効果が薄れてしまうものもあります。この記事では改めて便秘薬とは何なのか、便秘薬の種類、便秘薬の副作用と注意点についてお伝えします。
便秘薬とは

便秘薬は名前の通り、便秘を解消するために用いられる薬です。便秘というと何日も排便がないイメージがあるかもしれませんが、毎日便通があっても残便感があるなど不快な状態が続いている場合も便秘と呼びます。逆に数日に1度しか便通がなくても楽に排便ができ、スッキリ感があれば便秘ではありません。便秘薬は便の水分を増やすもの、便のかさを増すもの、大腸を刺激するものなど様々な種類が存在しています。
便秘薬の種類

便秘薬は飲み薬を中心に多くの種類が作られています。ここではそれぞれの便秘薬について簡単に説明をします。
浸透圧性下剤
腸内や便の水分を増やして、便を柔らかくします。
塩類下剤
塩類によって腸内に水分を引きつけます。水分を便が吸収することで便を柔らかく、ふくらませて排便を促します。お腹が痛くなりにくく、習慣性もないことから第一選択薬になりやすいです。高マグネシウム血症を起こす可能性があり、高齢者や腎臓障害の患者さんや長期服用には注意が必要です。代表的な薬は酸化マグネシウム(マグミット)、硫酸マグネシウム、水酸化マグネシウム(ミルマグ)。
湿潤性下剤
界面活性作用によって、便の表面張力を低下させて、便に水分を吸収させます。効果は他の下剤と比べると弱めであり、市販薬では刺激性下剤と組み合わせて配合されていることもあります。代表的な薬はジオクチルソジウムスルホサクシネート(ビーマス)。
膨張性下剤
腸管内で水分を吸収し、便のかさを増します。便が大きくなることで、腸を刺激して排便を促す効果も期待できます。食事量が少ないなどで、便が小さいために便秘を起こしている患者さんに有効です。代表的な薬はカルメロースナトリウム(バルコーゼ)。
上皮機能変容薬
腸管内の水分分泌を促して、便の水分量を増やして排便を促進します。2012年に承認された比較的新しい薬です。慢性便秘症ガイドライン2017では、浸透圧性下剤と並んで推奨度が強い薬となっています。代表的な薬はルビプロストン(アミティーザ)、リナクロチド(リンゼス)。ルビプロストンは妊婦さんへの使用は禁忌となっている点に注意が必要です。
胆汁酸トランスポーター阻害薬(IBAT阻害薬)
胆汁は肝臓で生成され、小腸の最後(回腸)で9割が吸収されるのですが、その吸収を阻害することで、腸管内に入ってくる胆汁の量を増やします。胆汁が大腸内に入ると水分分泌を起こし、その水分で便を柔らかくし、また大腸の動きを活発にして排便を促します。水分分泌を起こすことから、上皮機能変容薬に分類するケースもあります。2018年に承認された上皮機能変容薬よりも新しい薬です。代表的な薬はエロビキシバット(グーフィス)。
刺激性下剤
腸に作用して、腸の動きを活発にすることで排便を促します。よくドラマや漫画で下剤を盛られて、お腹がぎゅるぎゅる鳴ってトイレに駆け込むという描写がありますが、あのイメージです。腸を強制的に動かすため、効果は強力ですが、連続して使用していると効果が薄れてしまったり(耐性)、下剤を使用しないと排便できなくなってしまったりする点に注意が必要です。
小腸刺激性下剤
小腸で作用して排便を促します。現在は便秘解消に用いられることはほぼなく、食中毒や腸炎などを起こした際に、毒素を排出する目的で使用されます。代表的な薬はヒマシ油。
大腸刺激性下剤
大腸で作用して排便を促します。便秘で刺激性下剤と言った場合は大腸刺激性下剤を指すことがほとんどです。成分によって「アントラキノン系」「フェノールフタレイン系」「ジフェニルメタン化合物」に分かれます。
アントラキノン系
大腸内で分解され、腸の神経を刺激してぜん動運動を促します。長期服用は大腸の粘膜が褐色や黒色になる大腸メラノーシスになるため注意が必要です。代表的な薬はセンナ(アローゼン)、センノシド(プルゼニド)。
フェノールフタレイン系
小腸で胆汁に分解され、大腸粘膜を刺激してぜん動運動を促します。代表的な薬はフェノバリン。
ジフェニルメタン化合物
大腸内で分解され、ぜん動運動を亢進します。また、水分の吸収を抑えることで便の水分量を増やす効果もあります。代表的な薬はピコスルファートナトリウム(ラキソベロン)。
漢方
便秘に効果がある漢方薬も多く存在しています。便秘の種類や患者さんの体力の有無などによって適した漢方薬が異なるため、医師や薬剤師に相談するようにしてください。また、刺激性下剤と近しい効果のものもあり、そのようなものは漢方薬も同様に耐性など連続での使用に注意が必要です。
坐薬
坐薬は直腸に近いところで作用するため、直腸に便が詰まっているケースなどに有効です。また、飲み薬が使用できない場合にも使われます。効力は強く、即効性もありますが、刺激性下剤と同様に連続しての使用に注意が必要です。代表的な薬は、炭酸水素ナトリウム、無水リン酸二水素ナトリウム(新レシカルボン坐剤)、ビサコジル(テレミンソフト坐薬)。
浣腸
肛門から直接薬液を注入し、直腸粘膜に刺激を与えることでぜん動運動を亢進します。また、便を柔らかくすることや潤滑油としての効果も期待できます。坐薬よりもさらに即効性があり、こちらも刺激性下剤と同様に連続しての使用に注意が必要です。代表的な薬はグリセリン。
整腸剤
整腸剤は腸内の細菌バランスを整えるための薬です。乳酸菌、ビフィズス菌、酪酸菌など、様々な種類があります。ここまでの薬が便を排出する効果を期待しているのに対し、整腸剤は腸内環境を整えて、根本的に便秘を解決するための手段と言えます。代表的な薬はビオフェルミン、ラックビーなど。
便秘薬の副作用と注意点

便秘薬の服用によって、よく生じる副作用は次のようなものがあります。
- 腹痛
- 下痢
- 吐き気、嘔吐
- 腹部の膨満感
お腹に作用する薬のため、副作用はお腹に関するものが多いです。これらの副作用は薬の服用を止めれば治まりますので、副作用が辛い場合は他の薬を試すなどすると良いでしょう。
刺激性下剤の項目で触れた通り、刺激性下剤や坐薬、浣腸は刺激に慣れてしまう、薬に耐性がついてしまうなど、中長期の服用に注意が必要です。それ以外の薬は安全かというと、酸化マグネシウムでは高マグネシウム血症になる可能性があるなど、リスクをはらむ薬もあります。便秘薬を使うことで短期間に便秘が解消されれば問題ないですが、短期間で解消されない(解消されてもすぐに便秘になるケースも含む)場合は医療機関の受診をしてください。あなたにあった便秘薬の調整、根本的な解決のアドバイスなどをもらえるはずです。

便秘薬についてお伝えしました。作用の仕方で様々な種類の便秘薬がありましたね。刺激性下剤などは中長期連用することで、耐性ができて薬が効きにくくなる点に注意が必要です。他の薬でも長期の服用に注意しなくてはならないものもあります。ご紹介した便秘薬は整腸剤を除いて、根本的な解決をするものではありません。便秘薬を使っても便秘が解消しない、もしくは一時的にしか便秘が解消されない場合は、生活習慣を見直すなど根本的な解決を目指しましょう。改善方法についてはこの後に掲載する「便秘の原因と解消法」の記事をご覧ください。
関連ブログ記事
関連リンク
便秘(日本臨床内科医会)
便秘の治療方法(便秘のお悩み解消サイト イーベンnavi(EAファーマ株式会社)
便秘の予防や治療に用いられる薬(MSDマニュアル家庭版)